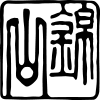金襴手とは、色絵陶磁器の上に金を定着させる装飾技法、およびその作品を指す。中国の宋代にはじまり、明朝から清朝にかけて隆盛を極めた。
日本では明朝の景徳鎮窯を範に、江戸の元禄年間より金襴手が登場する。金糸や切金箔を織り込んだ「金襴」の織物に似ていたため、我が国ではこの名で呼ばれるようになった。1694(元禄7)年に編纂された『万宝全書』には、すでに「染付金襴手」の記述が見られる。
金襴手のなかでも、細密精緻な赤絵の上に金彩を施したものは「赤絵金襴手」と称される。また、九谷の名工・九谷庄三は、明治初年に絵付に洋絵具を取り入れることに成功。洋絵具による上絵付と金彩を組み合わせた画風は「彩色金襴手」と呼ばれ、明治時代以降、九谷焼の主流となった。
金襴手には、金泥で線を描く「金描き」、金粉を散らす「金振り」、金箔を貼りつける「金貼り」などがある。
白絵の具を凸状に盛り上げる上絵付けの技法。またこれに使う白い盛り絵の具そのものを指す言葉でもある。繊細な唐草文用を白盛りで描くことにより、素地の白色との微妙な対比を表現することができる。
釉裏金彩とは、うつわの表面に金箔や金粉などの金彩を用いて紋様を表現し、その上に釉薬を掛けて焼き上げる技法のことである。
江戸時代以降、有田や九谷などの上絵付を得意とする産地で、金を用いた金彩の技法が独自に発展してきた。しかしながら、金彩にはひとつの難点があった。それは経年によって表面の金が摩耗したり、剥がれたりしてしまうことである。この問題を改善するために考えられたのが、金彩を施した上に釉薬を掛け、表面を釉薬のガラス質でコーティングするという発想であった。石川県工芸指導所を中心にさまざまな試みが重ねられたが、釉薬を掛けて最後の焼成を行った段階で、特定の色釉が消えてしまうなどの問題が発生し、なかなかうまくはいかなかった。
そうした状況を打破したのが、竹田有恒(1898~1976)である。昭和30年代、竹田は厚手の金箔を用い、金を釉薬のなかに閉じ込める技術を編み出した。
1966(昭和41)年、竹田は第12回日本伝統工芸展で「沈金彩萌黄釉鉢」を出品。「沈金」とは、金が沈んだように見える漆の技法で、この表現を竹田はやきものでやろうとしたのだった。しかし、やきもので沈金という名前は適切でないという、日本伝統工芸展鑑査委員であった人間国宝の加藤土師萌らの助言により、この技法は「釉裏金彩」と名づけられた。加藤もまたこの新しい技法に魅せられ、釉裏金彩を用いた作品を多く生み出した。
こうした先駆者たちの仕事に触発され、新たに釉裏金彩に挑んだのが、九州・嬉野の小野珀子(1915~1996)、九谷の二代松本佐吉(1905~1988)、そして錦山窯の吉田美統である。それまで釉裏金彩は地紋様や幾何学紋様の表現に使われていたが、吉田は厚箔(厚手の箔)と薄箔(薄手の箔)を用いて濃淡を出し、立体感のある表現を確立。花や蝶などの具象をモチーフに使い、独自の世界を切り拓いた。
釉裏金彩には、金が剥がれるのを防ぐという役割があるだけではない。釉薬のガラス質の被膜を通すことによって、金属的な強い輝きが抑えられ、金は品のある幽玄な煌めきを放つようになる。それが釉裏金彩の持つ大きな魅力である。
金消しは、まず「切りまわし」という金箔を裁断するときに出る切れ端ににかわ液を加え、糊状にしたものをすり潰すところからはじまる。途中、にかわが固まってきたら少量の湯を加え、さらに細かくすり潰していく。通常は掌を使ってするが、金粉の消費が多い錦山窯では、独自に改良した擂潰器を使い、この作業を行う。金が十分すり潰されたところで、熱湯を注いで水簸を数回繰り返し、細かい粒子の金粉を選り分ける。これを乾燥させたものが、上絵付に使う金粉となる。微粒の金粉も市販されているが、自家製のほうが細かく発色のよいものができるため、錦山窯では金消しは欠かせない作業となっている。