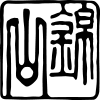錦山窯は、石川県小松市高堂町にある九谷焼上絵付を専業とする窯元です。1906(明治 39)年に初代吉田庄作がこの地に開業して以来、およそ 110 年の間、窯の火を絶やさずに作陶を続けてきました。17世紀に加賀藩の御用窯として発展した九谷焼は、五彩を駆使した色絵や金彩をあしらった金襴手など、細やかで絢爛華麗な絵付を特徴としています。明治時代には「ジャパンクタニ」と称されて海外にも広く輸出され、その技術や造形美は世界中から高い評価を受けてきました。
錦山窯では、九谷が育んできたさまざまな技法を受け継ぎ、現在の作陶に活かしています。なかでも、錦山窯が得意とするのは、金彩の技法です。彩色金襴手に長けていた初代から代々、金を使った絵付を特徴としてきました。三代美統は「釉裏金彩」の技法を高め、国指定重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定を受けています。そして四代幸央は伝統の技を継承しながら、時代に合った新しい彩色金襴手の表現を模索して日々研鑽しております。
錦山窯の初代吉田庄作(1888 〜 1948)のルーツを辿ると、高堂町の九谷絵付の草分けとされる小酒磯右衛門(1833 〜1900)にいきあたる。
磯右衛門は、佐野窯の斉田伊三郎(1796〜1868)に学び、1859(安政6)年に独立。のちに寺井で窯を開いた九谷庄三に招かれ、陶画工として数年ほど働いている。師である伊三郎は、多くの陶画工を輩出した若杉窯の出身で、上絵を二度焼成する技法を完成し、赤絵金襴手の発展に大きな役割を果たした人物として知られる。
伊三郎、磯右衛門の系譜に連なるのが、荒屋(現小松市荒屋町)の石浦伊三郎(生年末詳〜 1897)であり、その弟子の田中英亮(1870 〜 1951)である。そして、この田中英亮(のちに嶺山堂号す)が庄作の師となる人物である。
明治時代に入り、九谷焼は産業として栄え、1887(明治 20)年には日本の陶磁器貿易額の第一位となる。能美地方では、輸出向けの大量生産に備え、陶画分業場が設けられ、素地の製作と絵付の分離が推し進められた。そうした九谷焼の最盛期に田中英亮は独立し、多数の徒弟、職人を雇って手広く絵付業に乗り出した。
1900(明治 33)年、庄作は英亮の下に入門し、作陶を学びはじめる。数年の修業を終えたのちに金沢へ赴き、金粉を撒く 金振りという金沢絵付の技法を習得。そして 1906(明治 39)年、高堂町にて独立を果たした。
金の扱いに秀でていた庄作は、金振りを取り入れた墨山水や、金彩を用いた錦絵風を得意とした。金地を花紋様で埋めつ くした「花詰」という技法も手がけている。また、当時は草書体の文字を細密に描いた「細字」と呼ばれる技法も流行り出し、小田清山(1874 〜 1960)や田村金星(1896 〜 1987)などの名手が登場した時期でもある。庄作も窯の仕事として、他の職人が描いた百人一首の細字に人物画を描き、金描きを加えたものを多く制作している。折しも関東大震災により、横浜に進出していた九谷の貿易商が打撃を受け、内需拡大へと舵を切らざるを得ない時期であった。それが結果として絵付技術を向上させ、錦絵風の細密な色絵に金を使ったさまざまな技法を施す「高堂絵付」の隆盛につながった。
庄作には跡継ぎがいなかったため、末弟である清一(1905 〜 1941)が 1933(昭和 8)年頃に錦山窯二代となる。清一は牡丹や孔雀などの花鳥風月を取り入れた「金彩細描画」を得意とした。また、金が配給制となった戦時下には、1936(昭和11)年に設立された石川県工芸指導所の指導の下、青手九谷を用いた作品を制作。九谷のデザインを改良した多数の新しい作品を制作し、各種の美術展や工芸展に入賞している。
戦後の復興が進むなか、1941(昭和16)年に早世した清一に代わって、三代美統が窯を継ぐ。クラフト運動が盛り上がりを見せた昭和30年代にはデザインを学び、金彩を用いたモダンな作品も発表。昭和40年代には地元の陶芸家らと旭窯を起ち上げ、新製品のデザイン開発にも携わる。美統は1972(昭和47)年、人間国宝の加藤土師萌(1900〜1968)の遺作展で釉裏金彩の作品に惹かれ、試作をはじめる。1974(昭和49)年の日本伝統工芸展に釉裏金彩の作品で初入選し、以後花や蝶などの具象をモチーフとする独自の釉裏金彩の世界を確立。2001(平成13)年には、国の無形文化財保持者に認定される。
2007(平成19)年には、美統の長男である幸央が四代となる。幸央は、淡く重ねられた幾何学紋の色絵に金をあしらった作品を生み出し、新しい彩色金襴手の表現を追求している。
「金消し」という伝統的な金粉製法を独自に改良して上質な材料をつくり、筆で丁寧に手描きしていく。その手法は、再興九谷以来、幾多の画工の手を経て、連綿と受け継がれてきたものにほかならない。錦山窯の歴史とは、伝統を活かしながら、それをさらに独自の金彩表現へと代々昇華させてきた歩みなのである。
百年余りの長い歴史のなかで、錦山窯が育み、受け継いできたもの。それは、伝統的な技法だけにとどまらない。材料の製法や道具、種々の型や図案、そして花びらのように小さな盃から、抱えきれないくらいの大壺にいたるまで錦山窯で焼かれ、参考品として残されてきたものの数々。そうしたすべてが錦山窯の遺産である。これらの遺産を、この先の百年にどう受け渡していくのか。大きな問いを前に、錦山窯はいま新たな取り組みをはじめている。
その柱となるのが、新作「酒具-Shugu」シリーズの開発だ。伝統的な技法を見直し、現在の暮らしにふさわしいあり方を模索するとともに、窯のスタッフたちも育てる。そのためには、実際に新たなラインナップを打ち出していくことが必要だと考えたのだ。錦山窯のブランディングに携わるデザイナーの古庄良匡氏と当主の吉田幸央との間で話し合いが重ねられ、第一弾は酒器のシリーズを制作することに決めた。幸央は言う。「錦山窯の製品は金を使うため、値段を抑えるには限界があります。嗜好性もありながら、なおかつ日常的に使って楽しめるものにしたい。そう考えた結果、酒器というアイテムをつくることに決めました」
製品化にあたり、絵付だけでなく形から新たに考えるため、幸央の弟でありプロダクトデザイナーである吉田守孝が参加することになった。こうして2013年の夏、新たな取り組みが本格的に始動した。伝統工芸とプロダクトのよさを融合させながら、いかに時代を超えるものづくりをしていくか。錦山窯の挑戦はまだはじまったばかりである。